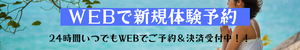第三講 ヴァイシェーシカ哲学
それでは、インド六派哲学の一つ、『ヴァイシェーシカ学派』についてみていきましょう。ヴェーダを実存論の立場から解釈した思想とは一体どのようなものだったのでしょうか。
ヴァイシェーシカ学派は紀元前2世紀ごろに成立しました。ヒンドゥー教の聖人であるカナーダによる「ヴァイシェーシカ・スートラ」を経典とし、ヴェーダを実在論、多元論の立場から解釈し、世界を説明しようとしました。一説には古代ギリシア哲学との交流があったとされ、元素に関する考え方などは双方において、影響しあったのではないかと考えられています。ヴァイシェーシカ学派は「六派哲学」の一つに数えられています。六派哲学とは、当時多様に存在していた哲学学派の中で現在も有用とされる6つの哲学の事です。時代ごとにその選定基準はコロコロと変わり、現在の形に落ち着いたのは1800年代にアーリアン学説で有名なマックス・ミュラーなどが選定したものが現在でも六派哲学として認められています。
ヴァイシェーシカ学派は、世界を実存論的・多元論的に説明しようと試みました。彼らは世界を「6パダールタ」に分類します。それが「実体」、「属性」、「運動」、「不変」、「特殊」、「内属」です。パダールタは英語ではCategoryと訳されます。しかし、アリストテレス的なカテゴリーとは少し意味合いが違います。アリストテレス的なカテゴリーには概念という性質が含まれます。例えば彼の著書『範疇論(カテゴリー論)』においては、実態とその他の様相(性質や関係)を分けました。しかし、ヴァイシェーシカ学派のパダールタにおける様々な事象はより広い範囲を言語に対応した実在であると考えるのです。
例えば6パダールタの1つ目である「実体」においては、9つの実態を認めます。
まずは四元素である地・水・火・風。次に虚空。古代ギリシアの元素論においては、エーテルとされたものに近いです。四元素が移動するための空間、と理解しても間違いではありません。また、虚空は音の属性だともいわれます。続いて時間・方角・位置関係や時間関係にかかわる要素です。そしてアートマン。これは自我と考えて問題ありません。重要なのは、ヴァイシェーシカ学派において、この9つの要素は全て実体だとされたことです。時間や方角も実体として捉えられ、さらには自我や心も実体だと言います。これらの実体が他のパダールタと影響しあうことで世界が構成されている。つまり、6パダールタで世界は説明できると考えたのです。
このような理論によってどのような帰結が生まれるか。例えば身体は原子でできているため、通常、カラダは原子であると考えるのが普通です。しかし、ヴァイシェーシカ学派においては、身体も原子もまた別の実体であると考えますので、身体と原子は別の実存で、それどころか身体と頭、耳、口なども別の実存だとするのです。これによって長らく疑問視されてきた、原子は目に見えないのに、なぜ原子が集まった身体は見えるのか?という疑問に対しても、原子と身体は別の実体だからというとんでもない角度から回答が可能になります。
ヴァイシェーシカ学派においての解脱は6パダールタの理解にあります。6つのカテゴリーによる世界への正しい理解が得られると無知が消え、あらゆるものに対する執着がなくなります。執着がなくなると、欲望や憎しみなどの必要がなくなり、そこから生じる善悪の行為がなくなり、それに伴う結果もなくなります。最終的に過去に積み重ねられた行為の結果(業)が消滅し、輪廻の繰り返しから解放され、解脱に至ると考えられました。
ヴァイシェーシカ学派は、言語と実体は完全に対応していると考えました。例えば、「兎に角」という言葉がありますが、この言葉は実在を原因にしないと生まれないと考えるのです。人間が実在を前提として兎の角というものを想像した時、彼らは兎の角も実存として認めます。他の学派はこのような実在論的姿勢を厳しく批判しました。ある額はからは爆発的に実在を増やしてしまう思想を揶揄し、「ヴァイシェーシカ学派の世界は実世界よりも広い言葉の世界である」と表現されました。行き過ぎた言葉遊びと捉えることもできますし、ヴィトゲンシュタインが提唱した「写像理論」に近い分析哲学的な思想だと考える事も出来ますね。
また、この学派の非常に面白いところは、『知覚も推論も正しい認識方法として認めた』ことです。例えば、西洋哲学史においては、経験(知覚)を正確な認識方法と考えたイギリス経験論と、推論を正確な認識方法と考えた大陸合理論が、お互いの正当性をめぐって激しい議論を交わしました。しかし、ヴァイシェーシカ学派においては、経験(知覚)と合理(推論)は矛盾しないと考えます。経験はありありと近くすることができるし、合理でたどり着ける推論の世界、例えば、「原子の世界などはヨガや瞑想によって知覚することができる。」これが彼らのロジックです。2000年後に激しい議論を生む帰納法と演繹法の対立にすごい角度から答えを提示していたことに、インド哲学の面白さを感じずにはいられません。
続いて、ヴァイシェーシカ学派と対をなす【ニヤーヤ学派】についてみていきましょう。
第四講 ニヤーヤ学派
ヴァイシェーシカ学派と対をなす思想がニヤーヤ学派です。瞑想や苦行ではなく、論理によって解脱を目指したニヤーヤ哲学とは一体どのようなものでしょうか。
ニヤーヤ学派はインドを代表する論理学でもあります。経典はアクシャパーダ・ガウタマが著したとされる「ニヤーヤ・スートラ」で、2世紀ごろに成立したと考えられています。その他、新ニヤーヤ学派とされる哲学の経典である、「タットヴァ・チンターマニ」などが有名です。インド思想では解脱への方法として瞑想薬業を上げるものが多いのですが、ニヤーヤ学派はそれらを否定し、論理の追求による解脱を目指しました。彼らは苦しみの原因を「誤った認識」に求めます。誤った認識があるからこそ執着が生まれ、それを源泉として妬みや欺きや貪りが生まれる。解脱に役立つものを正確に把握し、誤った認識を滅することで苦を消滅さえることができると考えたのです。そして、真理の認識必要な対象を12個定義します。その12の心理とは、「アートマン(我)」、「身体」、「感覚器官」、「対象」、「意識」、「思考器官」、「対象」、「意識」、「思考器官」、「活動(業)」、「欠陥」、「転生(輪廻)」、「結果」、「苦」、「解脱」です。これらすべてを正確に『知る』ことによって苦しみが滅すると考えたわけですね。とは言え、ここで問題が発生します。12個の把握すべき真理のうち、「アートマン(自我)」は直接認識することができません。なぜならば、認識を可能にしている主体がアートマンであり、西洋哲学で散々議論された通り、認識方法自体を認識することはできないからです。ニヤーヤの哲学者たちも同様の問題に悩まされたようですが、彼ら理性によってアートマンを推論しうると考えます。例えば欲求という感情を考えたときに、ある事柄に欲求が生まれるということは、過去に同種の快楽を感じているはずです。何かを得たいということは、その何かを得ると得をすることが「あらかじめ分かっている」からだと言うんですね。そして、そう感じるからには過去と現在において同一の主体が必要であり、それその者がアートマンだと推論することができるとします。至極当たり前な議論な気がします。そこまでして『自分』という主体を推論しなくても、そりゃ自分は過去も現在も同一の存在だよなと考えてもよさそうです。しかし、『アートマン』という概念は非常に厄介な存在で、アートマンを単に自我とか心として断定出来れば楽なのですが、厳密にはどの言葉も100%アートマンに対応することができません。仮にアートマンが自我なのだとしたら、輪廻によって次に生まれ変わった生命に宿る自我が連続性を帯びていることを説明できないからです。もっと魂よりの意味なのですが、魂ともまた違う。同じように、私たちは過去に経験したことが無いようなことにも欲求を感じることがあります。これを前世の経験から来る欲求だと仮定して考えると、輪廻を超えた同一性を持つものの存在を想像することができます。このようにして理性を論理的に発揮することで、解脱に必要な審理に到達することができると考えるのがニヤーヤ学派の立場です。ヴァイシェーシカ学派の解説でも触れましたが、ニヤーヤ学派も非常に分析哲学的な要素を持っています。
例えば、仏教などにおいては対象は観念の構造物であると考えます。一方でニヤーヤ学派は認識や言語は現実世界に完全に対応するという実存論的なものの見方をします。白い馬の白と馬はどちらも現実世界に実在すると考えるのです。だからこそ、世界に対応した言語野認識を論理的に研究することで、真理に近づくことができると考えたのです。まさに分析哲学的姿勢です。そのような立場のニヤーヤ学派ですから、論理的根拠のない思想を大変嫌いました。例えば、六派哲学の一つに数えられるヨーガ学派においては、解脱のための瞑想を推奨していました。そして、解脱によって永遠の幸せを手に入れられると考えたのです。ニヤーヤ学派は瞑想で解脱に至る根拠が一切ないと、これを否定します。同時に、永遠に幸福が続くなんてことはなく、論理的に考えたら永遠に続かないと考える方が自然だとし、もっと言えば、幸せを求めている段階で既に執着が発生して、その愛着は束縛となり解脱を阻害する要因となる。つまり幸せを目的とする解脱は矛盾していると言いました。解脱が目指すものは無であり、決して幸福ではない。あくまでも論理的に、事実を冷静に認識した上で、知識と論理によって解脱にたどり着くという姿勢を誇示したのです。一方で、論理的な推論よりも、信頼できる言葉である神の言葉、すなわちヴェーダに書かれた言葉の方が正しいとする宗教的な要素も持ち合わせており、この若干のこる曖昧さが西洋哲学との大きな違いであり、インド哲学特有の面白さではないかと思います。とは言え、ニヤーヤ学派の論理は、その後様々なインド哲学や思想に取り入れられることとなります。
それでは続いて、超絶難解な二元論【サーンキヤ学派】についてみていきましょう。
第五講 サーンキヤ学派
インド六派哲学のサーンキヤ学派についてみていきましょう。二元論的に世界の成り立ちを説明した思想とは一体どのようなものだったのでしょうか。
『サーンキヤ』とはインドの古い叙事詩マハーバーラタによると『知識によって解脱するための道』という意味を持ちます。『サーンキヤ』とはインドの古い叙事詩マハーバーラタによると『知識によって解脱するための道』という意味を持ちます。対になるヨガ学派が解脱への実践を担当するとすれば、サーンキヤ学派はその理論面を担当する思想と言えます。この学派の現存する最古の経典はイーシュヴァラクリシュナの『サーンキヤ・カーリカー』だとされていますが、それ以外にもサーンキヤの思想は多くの書物に散見されます。サーンキヤ学派は知識によって解脱を目指そうとします。ウパニシャッド哲学においてもそれは同じですが、これについて経典の作者であるイーシュヴァラクリシュナは「サーンキヤ体系における句を取り除く方法はウパニシャッドのそれよりも優れている」と語っています。では、その優れた思想とはどのようなものなのでしょうか。サーンキヤの思想では『因中有果説』を採用しています。これは『原因の中にはすでに結果が内在している』という考え方で、例えば土を取り上げたとき、既にそこには「陶器」という結果が内在している。というような考え方です。ある意味、決定論的な思想だとも言えます。その上で、彼らは【転変説(パリナーマ・ヴェーダ)】を主張します。これは現象世界の一切は、一つの実在が展開・変化して生成するという説です。それを踏まえたうえで、かなりややこしいサーンキヤの世界生成論を見てみましょう。まず、純粋精神とされる「プルシャ」を想定します。プルシャは「ただあるもの」であり、自分からは何もすることがありません。たった一つできるのが『見ること』。もう一つ世界の根本原質である「プラクリティ」を想定します。プラクリティはトリ・グナと呼ばれる3つの要素で成り立っていて、普段はそれらのバランスが平衝していて全く変化しません。プルシャがプラクリティを観照することで、これらのバランスが崩れます。具体的には、ラシャスの活動が激しくなるためだとされています。プラクリティのバランスが崩れることで、そこから原理が流出します。それによって知の働きの根源状態であるマハットまたはブッディが成立します。その後、自我意識であるアハーンカーラが生まれ、思考器官とも心ともいえるマナスが生まれ、感覚や行動、その他の微細な要素が表出します。面白いのはこの説の場合、一番最後に表れるのが世界を構成する主要素である五祖大元素だということです。ウパニシャッド哲学的に言えば、プルシャはアートマンに近いでしょう(二元論なので本来ウパニシャッド哲学に当てはめてはいけません)。つまり一番根源的なわたしの本質。とりあえずこれを真自我としましょう。サーンキヤの体系では、『真自我が生じることで、世界が生じる。』と考えます。これはドイツ観念論の特にシェリングあたりの思想と共通点があります。また、サーンキヤ哲学ではプラクリティから全てが生まれ出て、最後はそこに還っていくと考えられますが、これは現代の物理学でも近いような理論が唱えられていますし、スピノザの流出論とも親和性があるものと感じます。そして、彼らは輪廻の原因を、この思想を元に結なかなか体的に提示します。私たちの心のもう一つ奥にある『自我(アハーンカーラ)』は、無知によって『マハット』や『ブッディ』をプルシャだと誤認してしまうというのです。そのため、完全にプラクリティを逆戻りできなくなり、プラクリティの中で繰り返しが行われてしまう。これが輪廻の原因だと考えました。そのことから、まずは世界の成り立ちを正しく理解して、一番低次にある五大から逆向きに消滅させていく必要があると言いました。そして、自我が真自我(プルシャ)として完全に目覚め、プラクリティに対して完全に無関心になることで、輪廻から解放され、晴れて無の境地に達することができるとしたのです。そして、その行程においては知識が最重要ではあるものの、実践もそれなりに必要だと考えられました。それをノウハウとしてまとめたのがヨガ学派です。一説には夏目漱石がこのサーンキヤの思想に大きく影響を受けたと言われています。確かに『吾輩は猫である』の猫は主観でも客観でもないもっと俯瞰した客観の装置を担っています。これは非常にプルシャ的な考え方ともとらえられます。また、「草枕」にはこんな文章もあります。「余が眠りは次第に濃(こま)やかになる。人に死して、まだ牛にも馬にも生まれ変わらない途中はこんなであろう」これも非常にインド哲学的な描写だと言えます。
それでは次にて、ヨガ哲学を見ていきましょう。