テストステロンを知る
体内のテストステロン値が高い人ほど筋発達しやすいです。テストステロンのレベルが高い人は、筋力が伸びやすく、しかも体脂肪を減らし易いので、フィジーク系アスリートを含む様々なスポーツ選手(競技者)にとって有利な条件になります。テストステロンを高める目的でトレーニングを始めたという人はあまりいないかもしれませんが、実際には、ウエイトトレーニングを行うことで、テストステロンの分泌量は増加します。
そのため、筋発達を目的にウエイトトレーニングを行っている人たちは、トレーニングで筋繊維を傷つけ、体内のテストステロンを高めるという二つの事柄を同時に得ることができるというので、まさにウエイトトレーニングは一石二鳥です。
ただし、どんなトレーニング方法や運動でもいいというわけではなりません。テストステロンの生成を促すトレーニングもあれば、逆にマイナスになるような運動もあります。
今回は、テストステロンとトレーニングの関係を解説し、テストステロンの分泌を効率よく促し、理想の身体作りをしてきくヒントをご紹介します。
アメリカ国立衛生研究所は、テストステロンについて次のように記述しています。「テストステロンは重要な役割を持つ、性ホルモンである。男性にとっては、性欲、骨密度、体脂肪、筋肉量、筋力の増減に関与するだけではなく、赤血球や精子の生成にも関わる大切なホルモンです。
テストステロンは、男性ホルモンで、女性には無関係だと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。女性でも体内でテストステロンは生成あれているんです。その量はとても微量で男性のテストステロンの5%せぐらいにしか存在しません。
また、テストステロンの分泌量は性別だけでなく、同じ男性でも個人差が多いし、正常値にあってもそれに幅があり、上限に近い正常値と下限に近い正常値ではこれもまた大きな差があります。
正常値の上限に近い方は、下限に違い方よりも筋肉の発達速度が早く、仮に同じトレーニング、同じ食事をした人でもこの差は顕著に肉体に現れます。
テストステロンが正常なレベルで分泌されている分にはそう問題ではありませんが、正常値の下限に届かないようならば、様々な不調すら訪れる可能性があります。やる気がわかなかったり、性欲が低下したりするのも低テスト論が原因かもしれません。
テ ス トス テ ロ ン は 骨、筋 肉、脂肪 、脳 、心 血 管系 、前立 腺 、陰茎 な ど全身の 多 くの 臓器 や 組織 に 作 用 す る こ とが 知 られて い る 。 実際 、加齢 に伴 う血 中テ ス トス テ ロ ン 低下 、い わ ゆ る late−onset hypogonadism (LQH ) と骨 密度低 下 、筋 肉 量 減 少 、うつ 病 、認 知力低 下 、ED 、メ タ ボ リ ッ ク症 候群 な ど様 々 な障害 との 関 連性が 大 規模 な疫学 的研究 に より明 らか と され つ つ あ る 。さ らに は テ ス トス テ ロ ン 低一ドが 全 死 亡 率、が ん死 亡率 、心 血管系疾患 に 伴 う死亡 率 に 関 して 有意 に独 立 した 危 険因子 で ある とい う研 究 も報告 さ れ 、男性 に お け る テ ス トス テ ロ ン の 意義が 注 目 され て い る 。
伊藤直樹「テ ス トス テ ロ ン と代謝」(2010)
なんだか不調続きで、筋発達も思わしない場合は、試しにテストステロン測定の検査を受けてみても良いでしょう。
また、ウィリアム・クレーマー氏が行った研究では、次のようにもコメントされています。「テストステロンは、骨格筋にあるアンドロゲン受容体に結合する主要なアナボリック・ステロイドホルモンだ。また、骨格筋や神経組織にカタボリズム(崩壊)が起きるのを抑止する働きもあるため、テストステロンが骨格筋に作用する筋力、パワー、持久力、そして筋肥大作用が低下しにくくなる」と。
実際、筋発達とテストステロンの関係を明確に説明するのは難しいものもあるのですが、少なくとも、テストステロンは筋繊維を肥大させるため筋中へのタンパク同化作用を促す働きを持っています。そして、それげ結果的に筋肥大をもたらすことは間違いありません。
だとすれば、筋力トレーニングなどに励む皆さんにとって気になるのは、どうすれば体内でこのテストステロンが生成され、分泌されるのか、どうすればテストステロンの量を増やすことができるのかということでしょう。また、別のページでそのことについて解説していきたいと思います。
立川ヨガ 立川エリア唯一の溶岩ホットヨガスタジオ「オンザショア」
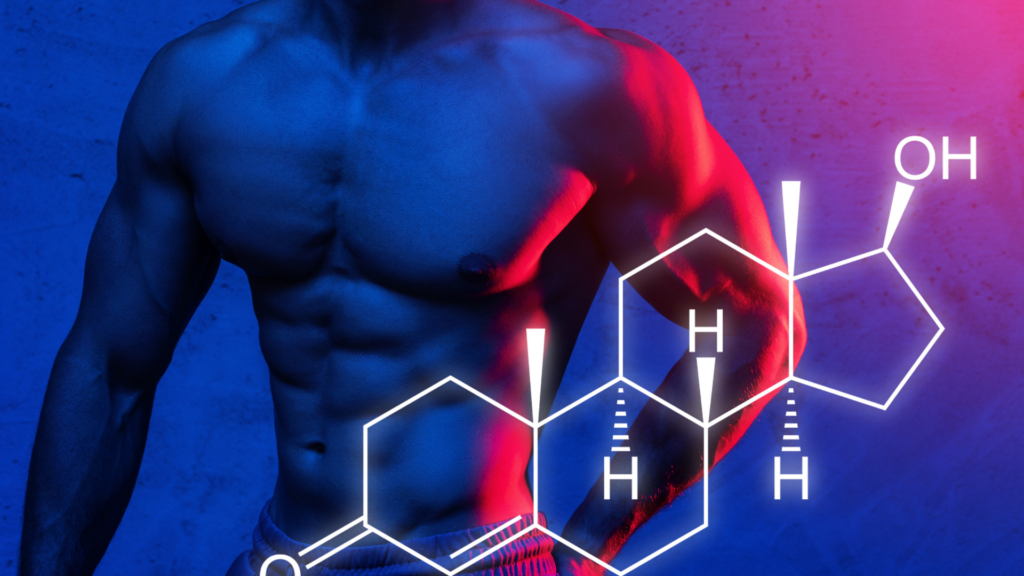
立川で学ぶ「ヨガの思想」
『ヨーガ・スートラ』を学んでヨガを深く知る(1)
『ヨーガ・スートラ』を学んでヨガを深く知る(2)
『ヨーガ・スートラ』を学んでヨガを深く知る(3)
『ヨーガ・スートラ』を学んでヨガを深く知る(4)
『ヨーガ・スートラ』を学んでヨガを深く知る(5)
『ヨーガ・スートラ』を学んでヨガを深く知る(6)
『ヨーガ・スートラ』を学んでヨガを深く知る(7)
『ヨーガ・スートラ』を学んでヨガを深く知る(8)
『ヨーガ・スートラ』を学んでヨガを深く知る(9)
『ヨーガ・スートラ』を学んでヨガを深く知る(10)
『ヨーガ・スートラ』を学んでヨガを深く知る(11)
『ヨーガ・スートラ』を学んでヨガを深く知る(12)
『ヨーガ・スートラ』を学んでヨガを深く知る(13)
『ヨーガ・スートラ』を学んでヨガを深く知る(14)
『ヨーガ・スートラ』を学んでヨガを深く知る(15)
バガヴァッド・ギーターの教え(ヨガの古典の経典を通してヨガを学ぶ)
バガヴァッド・ギーターの教え(ヨガの古典の経典を通してヨガを学ぶ)(2)
バガヴァッド・ギーターの教え(ヨガの古典の経典を通してヨガを学ぶ)(3)
バガヴァッド・ギーターの教え(ヨガの古典の経典を通してヨガを学ぶ)(4)
バガヴァッド・ギーターの教え(ヨガの古典の経典を通してヨガを学ぶ)(5)
バガヴァッド・ギーターの教え(ヨガの古典の経典を通してヨガを学ぶ)(6)
バガヴァッド・ギーターの教え(ヨガの古典の経典を通してヨガを学ぶ)(7)
バガヴァッド・ギーターの教え(ヨガの古典の経典を通してヨガを学ぶ)(8)
お勧めのヨガスタジオ
ヨガを定期的にレッスンしたい方や、豊富なバリエーションからヨガやピラティスだけで無く、ボクササイズやキックボクササイズ、HIITなどのエクササイズをしたい方には、立川駅徒歩1分、国内唯一の、イタリア溶岩石「バサルティーナ」を使用した、立川溶岩ホットヨガスタジオ「オンザショア」をおすすめしたいと思います。バサルティーナは火山石の中で最も美しい色調と流れがある溶岩石で、古代ローマの時代より建築家に愛されてきました。現在も国内外の有名ブランドや、美術館などにも好まれて利用されています。イタリア中部バーニョレッジョで採掘されるバサルティーナについて、また溶岩石の効果についてより詳しくお知りになりたい方はこちらをどうぞ!
| スタジオ名 | 立川エリア唯一の溶岩ホットヨガスタジオ「オンザショア」 |
| 住所 | 〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目14−10 エトロワビル 3F |
| TEL | 042-595-8039 |
| 事業内容 | 溶岩ホットヨガ、ピラティス、キックボクササイズ、ボクササイズ、HIIT、バトルロープ、総合格闘技、パーソナルトレーニングなど |
| 特徴 | 50種類の豊富なレッスンと早朝から深夜まで開催しているヨガのレッスンなど |
| 対応エリア | 立川、西国分寺、国分寺、国立、昭島、東大和、日野、青梅、あきる野、府中、武蔵村山、福生、羽村、八王子など |
| 定休日 | 年中無休 |
| URL | https://ontheshore.jp/ |
立川エリアで唯一の溶岩ホットヨガスタジオ「オンザショア」でアナタも今日からヨガを始めてみませんか?
| 【監修者】 | 宮川涼 |
| プロフィール | 早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻修士号修了、同大学大学院同専攻博士課程中退。日本倫理学会員 早稲田大学大学院文学研究科にてカント哲学を専攻する傍ら、精神分析学、スポーツ科学、文学、心理学など幅広く研究に携わっている。 |


