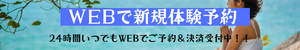ヨガの合間に学ぶ3分で読めるエッセイ(2)
原文が日本語の作品に限るか、それとも翻訳文も扱うかどうかで迷っているのですが、何か意見があればメールください。PS:ちなみに改行については私による編集が若干含まれていることをはじめにお断りさせていただきます。
加藤典洋『日本の無思想』
高橋源一郎『文学じゃないかもしれない症候群』
林達夫『思想の運命』
太宰治『如是我聞』
小野谷敦『もてない男』
秋田昌美『フェティッシュ・ファッション』
小林秀雄『常識について』
丸山真男『日本の思想』
富永健一『近代化の理論』
今道友信『西洋哲学史』
竹下敬次・広瀬京一郎『マルセルの哲学』
都筑卓司『物理学はむずかしくない』
高垣忠一郎『思春期の心理』
永井均『これがニーチェだ』
永井均『<こども>のための哲学』
~加藤典洋『日本の無思想』より~
トップへ
僕は、僕達の生きているこの日本の戦後の社会が、全体として、ある大きくて透明なお椀のようなものに覆われているのではないか、という気がしています。
お椀が透明だというのは、こういうことです。この社会は何かに覆われ、閉ざされている。でも、そこにいる人は、そのことに気づいていない。お椀がかぶさっているのですが、中にいる人はそう思っていない、いわばお椀がかぶさっているということの上にまたお椀がかぶさっているのです。
以前、漠然と、アンデルセンの「裸の王様」というのはよその国からきた巧妙な詐欺師にだまされて、裸のままに街に出た王様の話だと思っていました。裸だというのはみんなにわかっているのに、それをいうとまずいと街の人々黙っていると、一人の男の子が「王様は裸だ」といったため、王様は裸だということが街のみんなにバレてしまうのだと思っていたのです。
でもこれはそうじゃないんですね。
この童話では、王様が裸だということは、一人一人には、そう見えているのですが、そのみんながみんな、そう見えているのは自分にばかりで、ほかの人間には服が見えていると思っているために、そのことを人に黙っているのです。そういうことがあるために、一人の男の子が「王様は裸だ」というと、その声があっというまにひろがり、王様もそれを聞いて、具合が悪い思いをするという話なのです。
この話からこういうことがわかります。見えているということと、わかっているということとは、違うんですね。一人一人の人に裸が見えているのですが、それが自分にしか見えていないと思うと、その見えているということにいわば自分の承認が与えられない。オレのほうがおかしいのかな、と思ってしまう。すると、その見えていることは見えているという知覚にとどまって、その人の了解にならないのです。わかるということは、見えているという知覚だけではなく、他の人にもそう見えているはずだという了解が入っているのです。
さて、そうだとすると、ここに、第三の「裸の王様」を考えてみることができるでしょう。そこでは、王様の目にも、街の大人たちの目にも、王様の嘘の服が見えています、というか、見えているような気がしています。なんだかちょっと見ると裸のようだが、ほとんど透明の、素晴らしい服が王様の身をつつんでいるのです。それはむろん錯覚ですね。でも、みんなに見えていると思っていると、なんだかへんだな、と自分では思っても、その了解のほうが強くて、知覚に影響を与えてしまう。見えているような気がしてしまうのです。この第三の「裸の王様」では、その思い込みの錯覚状態が、その男の子が「王様は裸だ」というと、とたんに、魔法のように、とけていきます。
僕は、この列島に住む人々もそんな思い込みの錯覚状態の中にいるのではないかと思っています。一人一人が自分ではちょっとおかしいと思っているのに、誰もそういわないので、自分の思い込みのほうが大したことがないんだと思っている。それは、本当は嘘なのに、それを見ないふりをしているということとは違います。歯の神経が深くやられてしまうともう痛くないですね。そのように、そこでは嘘は、深まっていて、本当は嘘なのに、それが嘘だと見えていないのです。
~高橋源一郎『文学じゃないかもしれない症候群』より~
トップへ
『「有害」コミック問題を考える』(創出版)によれば、この事件の一連の経過はこうなっている―九○年夏頃、子供向けコミックに「有害」な性表現が多いから規制しろという住民運動がはじまった。八月には東京都が「性の商品化に関する研究」を発表し、「市販の雑誌に掲載されているマンガの半数以上に性的行為の描写がある」等と指摘した。それを紹介する形で、九月四日、朝日新聞が「貧しい漫画が多過ぎる」という社説を発表する。「ビッグコミックスピリッツ」前編集長白井勝也によれば「この日をスタートラインに、怒涛のように『ポルノコミック』粉砕の一大勢力が台頭してきた」のである。十月には「ヤングサンデー」の「ANGEL」の連載が休止となり、単行本の発売が無期延期となった。九一年になると、講談社・小学館・集英社のコミック三大出版社が連名で「有害」コミックの回収要請通知を出した。二月になると、仕上げとして警察が登場する。
都内で、マンガ同人誌を販売していた書店が「わいせつ図画販売目的所持」容疑で摘発され、つづいて発行者も逮捕された。三月には熊本、六月には岡山で、「有害」コミックを販売していた書店がやはり摘発・送検された。それは出版社・書店がびびるに充分な恫喝であり、現在、「有害」図書はほぼ完全に一掃されている。一次、鎮静化にむかった(ように見えた)「有害」コミック規制のキャンペーンは、七月あたりからまた活発となった。これが、五月の通常国会で採択されたコミック規制に関する請願(おれの数えたかぎりでは衆院十九件、参院四件)が「法制化」の検討段階に入っていることと連動しているかどうか定かではない――。
「有害」図書を規制しようという動きは、何年かの間をおいて、周期的に出現している。そしてその論理は、いつでも全く同じである。反対派の論拠もまた「表現の自由」を基礎にしてなされてきた。だが、今回、はじめて新しい要素が加わったのである。それが、「性の商品化」批判という論理であり、その結果、「表現の自由」派のくもゆきが怪しくなった。「性の商品化」批判と「表現の自由」の間で股裂きの状態になってしまったのである。
≪(東京都の調査を紹介した後で)こうした漫画や写真を幼い時から見せられて育つと、どんな人間になるのだろうか。文化の将来を考えて、そら恐ろしい気持ちにもなる。とくに強調したいのは、こうした現象を女性の立場で考えてみる、ということだ。今回の調査を分析した執筆陣は、性の商品化、とくに女性を「モノ」として見る風潮を厳しく批判していた。・・・男性の編集者や漫画家は、「物語の流れから必然の描写だ」「女性蔑視どころか、美しく描いている」などと反論する。しかし、「性交の場面がキス場面の二倍以上もある」といった調査結果を読むと、商売優先、そして発想の貧困、と思わざるをえない。(そして、貧しい漫画の対極に手塚治虫があるとして)もちろん、低劣であることを理由に、法律や条例で規制するべきではない。問題の多い雑誌などがあっても、話し合いと、出版側の自制で解決していくべきだ。・・・(朝日新聞社説)
「有害」コミック規制派の論理が、この朝日社説をなぞるように存在しているのは、この社説を参考にしたからとしうよりも、これがきわめて「常識」的な論理であるからだろう。ここで使われている「貧しい」ということばには、およそ二つの意味が含まれている。その一つは「質として貧しい」ということだ。もっとわかりやすくいうなら「クズだ。下手糞だ。商売のことしか考えてない」ということだ。この論理の前提となっているのは「この世には豊かで芸術的な優れた作品がたくさんあり、それは保護されるべきだが、クズにはそんな特典を与えることはない」という発想であり、それは、おれの考えでは、表現がわからない人間が表現に関して持っているもっとも大きな妄想の一つなのだ。
かつて、SF作家のスタージョンは「SFの九○%はクズである」といった。あの希代の読書家であった中島梓もどこかで「読んだ本の九割はクズ」といったことがある。この「九○%」が実際には「九九%」なのか「八八%」なのか、おれにはわからない。だが、人間が関与する表現の大半がクズであることには、統計など読まずじっさいその表現に接している人間にとって自明のことなのだ。「貧しい」のは漫画だけではない。文化は「クズ」の集積そのものなのである。もし「表現の自由」というものがあるとするなら、それは「クズである自由」なのだ。それがわからないなら、文化について口出しすべきではないのである。
「貧しい」の含んでいるもう一つの意味は「方法が貧しい」ということだ。これはもっとわかりやすくいうなら「性を描くといったって、こんなもの劣情を刺激するだけのただのポルノじゃないか」ということだ。おれには、一つ一つの作品の個別性を無視したこの種の意見に嫌悪を感じるが、あえて規制派のいうように「有害」コミックがポルノであると仮定してみよう。ポルノグラフィーはもともと「ユートピア文学」の一種であるとされている。それは文学でありながら、同時に文学が抱えこんだ、宿命のライバルであった。ポルノグラフィーの最大の傑作はサド侯爵によって書かれたいくつかの著作でだが、かれの作品には、おれたちが「文学」という言葉からイメージする肯定的なもの一切と相いれないものが存在している。
たとえば、それは「人格を毀損する自由」であり、もちろん、こんな自由は誰によっても擁護されることはない。だが、やっかいなことに、サドが想像の中に構築したこの「自由」は、どんな肯定的な「自由」よりも大きな開放感を人に与えることができるのである。もちろん、「有害」コミックの大半はサドの確信もない、お手軽な、無限に薄められたポルノグラフィーにすぎない。だが、人はどんなに薄められていても、その「毒」を嗅ぎわけることができる。我々にはポルノグラフィーが必要なのだ。
最後に「青少年に与える悪影響」についてひとことだけ書いておく。かつて青少年であったおれの経験からいって、あんなもので悪影響を与えるのは奇蹟に近いだろう。もちろん、あらゆることが「性的非行」の原因となりうるのだから、「有害」コミックがその原因の一つとなることが皆無であるとはいわない。だが、おれのような精神医学の素人でも、「有害」コミックそのものよりその規制を叫ぶ連中の有形無形の抑圧の方が遥かに「性的非行」の原因となる可能性が高いということだけは断言できる。コミックの、なかんずく「有害」コミックのファンのひとりとして、おれは「青少年の性的非行防止」のために、「有害」コミック規制派の規制を要求する。
~林達夫『思想の運命』より~
トップへ
最近、センセーションを呼んだ事件の一つは、わが国におけるもっとも「輝かしき」理論家の一人が、事もあろうに衆人環視の中でもっとも破廉恥極まる「剽窃家」として弾劾された一事である。「センセーションを呼んだ」というのはその告発者がほかならぬ一女性であり、しかもその弾劾文たるやその検事的峻烈さとヨーロッパ的学殖とで世人を驚かせるものがあったからである。だが、我々はこの女性にしてこの事のあるのを別に不思議としなかった。けだしこの女性――聖女カテリーナの正義感とスタール夫人の博識とを兼ね備えたこの女性は、我々の間では既にもっとも仮借なき「職業的」廓清家として聞こえていたからである。(誤解を防ぐためにいっておくが、「職業的」という言葉を私はレーニンのいわゆる職業的革命家と同じように尊敬的意味で使っている。)
彼女は曽てその得意とするドイツ語の造詣を駆使して徳永直の『太陽のない街』のドイツ語版の「誤訳」なるものを摘発したことがあるし、また彼女の一寸した随筆の端々をも学者や文芸家のインチキ征伐の舞台として利用することを決して忘れたことのない人だからである、「インチキな今の時世に」このような篤志な女流警世家のいることはまことに頼もしさの限りである。
だが、大いに意を強ようするものの、また多少の懸念なきを得ない。推賞すべき廓清カンパニーアの遂行も一歩あやまればピントはずれの暴力行為となることは、中世の「神聖なる」宗教裁判が廓大的に我々にも見せてくれている。私は板垣直子夫人を以てジャンヌ・ダルクを火刑台に上せたかの宗教裁判官に比そうとは思わないし、況んやわが三木清をもって無辜なオルレアンの少女に比するが如き「冒涜」は敢えてしないであろう。私はかかる傾倒をなすほど非常識ではない。だが、板垣夫人の秋霜烈日の如き断罪的方法には、正直いって、多少ともかの中世的スコラ的宗教裁判方法に似通う形式主義、機械主義、末梢主義への気懸河ないとはいえないのである。かかる方法の杓子定規的適用が場合によってはどんなことになるか。それを示そうとするのがこの小文の第一テーマである。
若し板垣夫人のように一切の「剽窃」がインチキであり不徳義であるとしてこれを犯罪視せねばならぬとしたなら、今日果して幾人の学者や文芸家がこの破廉恥な汚名を免れるであろうか。私は文部省に「精神文化研究所」のような「評判高き」機関を設置する意気があるなら、それを学術的文芸的剽窃の調査機関の設立にでも宛てた方が(後章で述べるような理由からしても)遥かに有益だったろうと思う。
不幸にしてかかる機関がまだないから正確な統計はわからないが、私の推測するところでは「剽窃」から身の潔白を説明することのできる文筆の士の数は予想外に少ないのではないかと思う。寡聞な私でさえ、(板垣夫人の意味での)剽窃の場合なら公の論文や作品の中から十や二十なら立ちどころに挙げることができる。(先ず下は私自身の場合から始めて上はわが国におけるもっとも独創的な世界的哲学者の場合に至るまで。)私はいわゆる剽窃は、わが国において決して二三の例外的変態現象ではなくして、むしろそれは一般的正常現象であるとさえ断言して憚らないものである。
否、それは単にわが国の今日の現象であるばかりではない。多少とも西洋の学問芸術を聞きかじった者であるなら、古来その独創性を以て鳴っている西洋の大文豪や大学者のくににさえ、証拠歴然たる剽窃行為を見出すのに少しも困難しないであろう。
というのは、板垣夫人の多くのヨーロッパ的先駆者たちが克明にそれを検べ出してくれているからである。シェークスピアやモリエールやスタンダールの場合は文芸家のうちの最たるものであり、思想家のうちにもプラトンやデカルトをはじめ幾多の例を数えることができる。
二流三流に至れば剽窃はもっと繁くなって、巨大な数に上るであろう。そうしてみると、剽窃は大きくいえば人類社会の共通的現象であるともいえることになる。インチキ師は、他人の思想や文句の泥坊は、無数に世界を横行しているのだ!何という恥ずべき犯罪の世界であろう!これでは博学なる板垣夫人が何千人いたってとても清掃しきれるものではない。しかも夫人の先駆者たちがあんなに厳しく弾劾しておいたのに、その剽窃家のシェークスピアやモリエールやスタンダールが依然としてイギリス文学やフランス文学の王座を占めているとは!
私がこんなことをいいだしたのは、いわゆる剽窃にはピンからキリまであるということがいいたかったからだ。若し他人の労作を無断でそのまま踏襲することがすべて不徳義であり、摘発に値するとしたなら・・・二つの例を挙げて夫人の判断を乞いたい。
一つはこんな例を挙げて甚だ礼を失する嫌いがあるが、若しこのやり方でゆくと「公人として」の夫人は彼女の夫君をどうしても槍玉にあげなくてはならないということだ。けだし板垣鷹穂氏の美術研究書を豊富に飾っている挿画は、その大半はヨーロッパ人の研究書乃至アンダーソン等々の作品からの転載であるが、それは無断で行われているからである。ところがヨーロッパではかかる無断転載は法律的に堅く禁じられ、これを犯すものは一種の剽窃罪を以て法廷に訴えられることは、博学なる夫人のよく知るところであろう。
いま一つの例はもっと朗らかである。――フランス浪漫派の一寸名のある劇曲家にピエル・ルブランという作家がいた。この男は若いときにシルラーの『マリー・スチュアート』を断然剽窃して同名の戯曲を書いた男だが、さてその晩年のこと、イタリアの一名女優がパリを訪問した際、一夜その演技を見んとて某劇場に赴いた。その夜の出し物は実に他ならぬイタリア語によるシルラーの『マリー・スチュアート』であったのだ。見ているうちに、八十歳の老ルブランは額に手をあてて歯のない口をもぐもぐさせながらつぶやいた。――何だか見覚えがあるぞ!
耄碌した彼には六十年前の自作のことが中々思い出せなかったのだ。況んやシルラーの原作のことなど完全に忘却していた。やがてのことにやっと自作のことを思いだした。そして叫んだ。
――怪しからん!こいつはわしの悲劇を剽窃しよったな!
そして彼はこの「剽窃」の仕方が実になっていないと傍の者にいい放った!
板垣夫人よ、世の中にはこんなにすばらしい剽窃家もいるのです。あなたはこの年寄を向きになって弾劾する気になれますか?
~太宰治『如是我聞』より~
トップへ
他人を攻撃したって、つまらない。攻撃すべきは、あの者たちの神だ。敵の神をこそ撃つべきだ。でも、撃つには先ず、敵の神を発見しなければならぬ。ひとは、自分の真の神をよく隠す。これは、仏人ヴァレリイの呟きらしいが、自分は、この十年間、腹が立っても、抑えに抑えていたことを、これから毎月、この雑誌(新潮)に、どんなに人からそのために、不愉快がられても、書いて行かなければならぬ、そのような、自分の意志によらぬ「時期」がいよいよ来たようなので、様々の縁故にもお許しをねがい、或いは義絶も思い設け、こんなことは大袈裟とか、或いは気障とか言われ、あの者たちに、顰蹙せられるのは承知の上で、つまり、自分の抗議を書いてみるつもりなのである。私は、最初にヴァレリイの呟きを持ち出したが、それは、毒を以って毒を制するという気持もない訳ではないのだ。私のこれから撃つべき相手の者たちの大半は、たとえばパリイに二十年前に留学し、或いは母ひとり子ひとり、家計のために、いまはフランス文学大受け、孝行息子、かせぐ夫、それだけのことで、やたらと仏人の名前を書き連ねて以て、所謂「文化人」の花形と、ご当人は、まさか、そう思ってもいないだろうが、世の馬鹿者が、それを昔の戦陣訓の作者みたいに迎えているらしい気配に、「便乗」している者たちである。また、もう一つ、私のどうしても嫌いなのは、古いものを古いままに肯定している者たちである。新らしい秩序というものも、ある筈である。それが、整然と見えるまでには、多少の混乱があるかも知れない。しかし、それは、金魚鉢に金魚藻を投入したときの、多少の混濁の如きものではないかと思われる。それでは、私は今月は何を言うべきであろうか。ダンテの地獄篇の初めに出てくる(名前はいま、たしかな事は忘れた)あのエルギリウスとか何とかいう老詩人の如く、余りに久しくもの言わざりしにより声しわがれ、急に、諸君の眠りを覚ます程の水際立った響きのことは書けないかも知れないが、次第に諸君の共感を得る筈だと確信して、こうして書いているのだ。そうでもなければ、この紙不足の時代に、わざわざ書くてもないだろう、ではないか。
一群の「老大家」というものがある。私は、その者たちの一人とも面接の機会を得たことがない。私は、その者たちの自信の強さにあきれている。彼らの、その確信は、どこから出ているのだろう。所謂、彼らの神は何だろう。私は、やっとこの頃それを知った。
家庭である。
家庭のエゴイズムである。
それが結局の祈りである。私は、あの者たちに、あざむかれたと思っている。ゲスな言い方をするけれども、妻子が可愛いだけじゃねえか。
私は、或る「老大家」の小説を読んでみた。何のことはない、周囲のごひいきのお好みに応じた表情を、キッとなって構えて見せているだけであった。軽薄も極まっているのであるが、馬鹿者は、それを「立派」と言い、「潔癖」と言い、ひどい者は、「貴族的」なぞと言ってあがめているようである。
世の中をあざむくとは、この者たちのことを言うのである。軽薄ならば、軽薄でかまわないじゃないか。何故、自分の本質のそんな軽薄を、他の質と置き換えて見せつけなければいけないのか。軽薄を非難しているのではない。私だって、この世のもっとも軽薄な男ではないかしらと考えている。何故、それを、他の質とまぎらわせなければいけないのか、私にはどうしても、不可解なのだ。
所詮は、家庭生活の安楽だけが、最後の念願だからではあるまいか。女房の意見に圧倒せられていながら、何かしら、女房にみとめてもらいたい気持、ああ、いやらしい、そんな気持が、作品の何処《どこ》かに、たとえば、お便所の臭いのように私を、たよりなくさせるのだ。
わびしさ。それは貴重な心の糧だ。しかし、そのわびしさが、ただ自分の家庭とだけつながっている時には、はたから見て、頗るみにくいものである。
そのみにくさを、自分で所謂「恐縮」して書いているのならば、面白い読物にでもなるであろう。しかし、それを自身が殉教者みたいに、いやに気取って書いていて、その苦しさに襟を正す読者もあるとか聞いて、その馬鹿らしさには、あきれはてるばかりである。
人生とは、(私は確信を以て、それだけは言えるのであるが、苦しい場所である。生まれて来たのが不幸の始まりである。)ただ、人と争うことであって、その暇々に、私たちは、何かおいしいものを食べなければいけないのである。
ためになる。
それが何だ。おいしいものを、所謂「ために」ならなくても、味わなければ、何処に私たちの生きている証拠があるのだろう。おいしいものは、味わなければいけない。味うべきである。しかし、いままでの所謂「老大家」の差し出す料理に、何一つ私は、おいしいと感じなかった。
ここで、いちいち、その「老大家」の名前を挙げるべきかとも思うけれども、私は、その者たちを、しんから軽蔑しきっているので、名前を挙げようにも、名前を忘れていると言いたいくらいである。
みな、無学である。暴力である。弱さの美しさを、知らぬ。それだけでも既に、私には、おいしくない。
何がおいしくて、何がおいしくない、ということを知らぬ人種は悲惨である。私は、日本の(この日本という国号も、変えるべきだと思っているし、また、日の丸の旗も私は、すぐに変改すべきだと思っている。)この人たちは、ダメだと思う。
芸術を享楽する能力がないように思われる。むしろ、読者は、それとちがう。文化の指導者みたいな顔をしている人たちのほうが、何もわからぬ。読者の支持におされて、しぶしぶ、所謂不健康とか言う私の作品を、まあ、どうやら力作だろう、くらいに言うだけである。
おいしさ。舌があれていると、味がわからなくて、ただ量、或いは、歯ごたえ、それだけが問題になるのだ。せっかく苦労して、悪い材料は捨て、本当においしいところだけ選んで、差し上げているのに、ペロリと一飲みにして、これは腹の足しにならぬ、もっとみになるものがないか、いわば食慾に於ける淫乱である。私には、つき合いきれない。
何も、知らないのである。わからないのである。優しさということさえ、わからないのである。つまり、私たちの先輩という者は、私たちが先輩をいたわり、かつ理解しようと一生懸命に努めているその半分いや四分の一でも、後輩の苦しさについて考えてみたことがあるだろうか、ということを私は抗議したいのである。
或る「老大家」は、私の作品をとぼけていていやだと言っているそうだが、その「老大家」の作品は、何だ。正直を誇っているのか。何を誇っているのか。その「老大家」は、たいへん男振りが自慢らしく、いつかその人の選集を開いてみたら、ものの見事に横顔のお写真、しかもいささかも照れていない。まるで無神経な人だと思った。
あの人にとぼけるという印象をあたえたのは、それは、私のアンニュイかも知れないが、しかし、その人のはりきり方には私のほうも、辟易せざるを得ないのである。
はりきって、ものをいうということは無神経の証拠であって、かつまた、人の神経をも全く問題にしていない状態をさしていうのである。
デリカシィ(こういう言葉は、さすがに照れくさいけれども)そんなものを持っていない人が、どれだけ御自身お気がつかなくても、他人を深く傷つけているかわからないものである。
自分ひとりが偉くて、あれはダメ、これはダメ、何もかも気に入らぬという文豪は、恥ずかしいけれども、私たちの周囲にばかりいて、海を渡ったところには、あまりいないようにも思われる。
また、或る「文豪」は、太宰は、東京の言葉を知らぬ、と言っているようだが、その人は東京の生まれで東京に育ったことを、いやそれだけを、自分の頼みの綱にして生きているのではあるまいかと、私は疑ぐった。
あの野郎は鼻が低いから、いい文学が出来ぬ、と言うのと同断である。
この頃、つくづくあきれているのであるが、所謂「老大家」たちが、国語の乱脈をなげいているらしい。キザである。いい気なものだ。国語の乱脈は、国の乱脈から始まっているのに目をふさいでいる。あの人たちは、大戦中でも、私たちの、何の頼りにもならなかった。私は、あの時、あの人たちの正体を見た、と思った。
あやまればいいのに、すみませんとあやまればいいのに。もとの姿のままで死ぬまで同じところに居据わろうとしている。
所謂「若い者たち」」もだらしがないと思う。雛段をくつがえす勇気がないのか。君たちにとって、おいしくもないものは、きっぱり拒否してもいいのではあるまいか。変わらなければならないのだ。私は、新らしがりやではないけれども、けれども、この雛段のままでは、私たちには、自殺以外にないように実感として言えるように思う。
これだけ言っても、やはり「若い者」の誇張、或いは気焔としか感ぜられない「老大家」だったなら、私は、自分でこれまで一ばんいやなことをしなければならぬ。脅迫ではないのだ。私たちの苦しさが、そこまで来ているのだ。
今月は、それこそ一般概論の、しかもただぷんぷん怒った八ツ当たりみたいな文章になったけれども、これは、まず自分の心意気を示し、この次からの馬鹿学者、馬鹿文豪に、いちいち妙なことを申上げるその前奏曲と思っていただく。
私の小説の読者に言う、私のこんな軽挙をとがめるな。
~小野谷敦『もてない男』より~
トップへ
一九九○年の秋、私は申し込みが遅れて大学の寮に入れなかったため、月五五○カナダドルというかなり吹っかけられた値段で借りたヴァンクーバーのベースメント・スウィートで、文化人類学者・山口昌男の『知の遠近法』という本を読んでいた。これは一九七五年から七六年にかけて『中央公論』に連載された思想時評をまとめたものらしかった。私が読んでいたのは、その年、「同時代ライブラリー」として岩波書店から復刊されたものだった。
その第二章は、「噂がひとを襲うとき」と題されて、どうやらその当時起こったらしい、大学教授二人による教え子強姦事件を主に取り上げていた。しかしなにしろその時点で十五年も前の事件であり、かつ当時中学一年生だった私の記憶にあろうはずもなく、事件がどのような性質のものかよくわからないまま、山口のメディア評を読むのは、いささか隔靴掻痒の気味があった。
山口は、全体としては、こういう事件をめぐっては怪しげな噂が飛び交うもので、それを拾って煽情的に書き立てる週刊誌ジャーナリズムを批判する意図を持っていたらしい。とはいえ、強姦事件そのものについては、加害者とされる教授たちにだいぶ同情的であるらしく、被害者である二十六歳くらいの女子大学院生が、夜半教授のマンションへのこのことついていって酒を飲む以上、性行為があるくらいの覚悟はあってしかるべき、それを告訴するなどというのは非常識だ、という論調であった。
さらに作家・筒井康隆が『太陽』に書いた「強姦してもいい場合」というコラムもほぼ同趣旨で、山口は次の部分を引用していた。
とにかく、性行為という生産的行為、強姦という文学的行為をしてくれた人物への憎しみから、告訴というは破壊的行為に走るようでは、大学院で文学をやる価値などまったくない人間といってよい。・・・憎しみだけで二教授の文学的業績を葬ろうとするのは・・・最低だし、そもそも二教授の文学的業績を認めていなかったことになり、やっぱり大学院での勉強は無駄だったのだ。
もしかりにこの女性が文学に縁のない人間であったとしても、満二十六歳、かぞえどしで二十七か二十八のオールド・ミスの貞操が、二教授の社会的生命及び学問的業績及びその家族の生活をおびやかすほど価値があるものかどうか、自分で判断がつかないのか。(『太陽』一九七五年九月)
そして山口は、「判断力にゆとりのある人間なら、だいたいこの結論を妥当なものと認めることができるであろう」としている。
私は、へええ、と思った。事実から言えば、一九九○年当時、北米の大学に、こういうことの言える雰囲気はなかった。おそらく日本でも難しかっただろう。それにしても、もうひとつ気になったのは、「強姦という文学的行為」という箇所である。なぜ強姦は文学的行為なのだろうか。いずれにせよ、この事件についての詳細がわからなかったし、筒井の文章も全文を入手することはなかった。そのうち考えてみることにしよう、と思って、この文章は八年間私の頭のなかに引っかかっていた。
その間、強姦に関してはいろいろあった。別に私が強姦したとか訴えられたとかいうわけではないが、たとえばカナダにいたころには、同じ寮で強姦事件が起こって加害者の男が退寮させられたりもしたし、「アクエインタンス・レイプ」つまり知り合いによる強姦がいちばん多い、というようなことも聞いた。
カナダに帰ってからは、志賀直哉の『暗夜行路』のなかで起こる強姦事件について、あれは女のほうで誘惑している、と解釈するアメリカ人の女性研究者の意見も聞いたりして、アメリカにもこういう人がいるのか、と妙に感心したりした。
もちろんことは「フェミニズム」に関ってくるのであって、山口さんフェミニストからの抗議を受けたりしなかったのか、とか、今なら猛攻撃を受けるかもしれない、とか思ったのであった。フェミニストの考えは、だいたい、男の部屋へのこのこ入っていったからといって強姦されるいわれはない、それは強姦する男が悪い、というものではなかったかと思う。だからこそ、カミール・バーリアという女性学者が登場して、男の部屋へ入っていくような女は強姦されてもしかたがない、とぶちあげて物議を醸したのである。
それで今回ようやっと、当時の資料を入手できた。といっても大阪府立図書館で手に入れたのは『週刊新潮』の記事と筒井の文章だけなのだが、帰りの電車のなかでコピーを読みながら、これだけでいいのではないか、と思った。
『週刊新潮』によると、事件が起きたのは一九七五年三月十四日。某私立女子大の大学院日本文学科修士課程卒業生と在学生によるお別れコンパがさる中華料理店であったが、教授たちは教授会が長引いて八時半ごろ顔を出し、店は九時で閉店だったので、近くのバーへ移って二次会。さらに小料理屋で三次会になったときには、問題の二教授(当時二人とも四十三歳)と二人の院生だけになっていた。この店を出たのが十二時過ぎで、教授二人が、「もう電車がないぞ。近くにいい場所がある」と言って四人でタクシーに乗って、着いたのがその教授の仕事場であるマンション。ここで四人で飲んでいるうち、一人の院生が意識を失い、その間に強姦された、というのが女子院生の主張。それから彼女が告訴した、という段取り。
山口や筒井のように割り切れないのが、夜中に男の部屋へ行って酒を飲んだといっても、この場合男二人、女二人だったからである。男一人、女一人だったら、いかな相手が教授でも、この院生がのこのこついていったりはしなかったはずだ。ただ筒井というのはもちろん露悪的な作家であるので、この文章をあまり真面目に受け取るべきではないかもしれないが、山口は大まじめである。
さらに、「強姦が文学的行為」とはどういうことか?察するに、故・永山則夫が日本文藝境界に加入を望んで拒否されたとき、抗議して柄谷行人、故・中上健次とともに協会を脱会した際に筒井が述べた、「文学は悪と密接な関係がある」みたいな、要するに反社会的な行為が文学的だといった観念と、デリダが『尖筆とエクリチュール』で論じた、女性器の誘惑し退けるという両義的な性格が強姦に際して現われるとか、そういうことを考えていたのかもしれない(当時の筒井がデリダを読んでいたかどうかは疑問だが)。しかしそうなると、筒井の文章には矛盾撞着がある。なぜなら、前のほうではこう書いているからだ。
男性の多くはぼくと同じ考えかたをしている。健全な社会人である数人に訊ねてみたら、「ふつう、ああいう場合、やっちゃいますよねえ」と、全員が答えた。
そうなると、両教授は、「健全な社会人」の「ふつう」の行動をしたわけであって、なにちっとも文学的な強姦などではないのである。
さらに、山口が引用した部分などは、大学の文学部教授が、あるいはその業績が、筒井の考える「文学」に繋がるものだと考えている点で噴飯ものである。筒井の言うような「文学」は、大学の文学部などには稀に存在するだけだ、ということは、その後『文学部唯野教授』を書いた筒井には、今では了解済みのことだろうが。
その上、二十六歳という妙齢の女性を「オールド・ミス」などと呼ぶのは、私には許しがたい。だいたいオールド・ミスという呼称自体が差別的である。三十過ぎの独身女性が時にどれほど魅力的か、筒井は知らないのかっ!
要するに二人の女子院生もあまり賢明とは言えない。上述したように相手が二人、こっちも二人だったからといって十二時過ぎまで酒飲んでいていいことにはならない。『週刊新潮』によると、院生の父親は「相手の誘いにのった娘がウカツだったなどといえるでしょうか。自堕落だと非難できますか」と訴えているが、ウカツである。
しかしだからといって強姦した教授連に同情する気など私にはまったく起こらない。夜中に教授の部屋で酒飲んで意識を失う女子院生が無防備であるのと同じように、これを連れ込んで強姦する教授連もウカツなのである。筒井は言っている。
強姦にしろ和姦にしろ、深夜自分の部屋にまでついてきた女性とセックスしなかった場合、その理由はふつう、次の三つしかない。
一、その女性が醜い女であったため。
二、酒の飲み過ぎなどで、性的不能だったため。
三、母親とか姉妹とか自分の娘とかであったため。
三を除き、一、二の理由で女性を抱くとか襲うとかしなかった場合、これはその女性に対する侮辱になる。
どうも筒井にはまだ「近代」というものが訪れていないようだ。山口も筒井も、完全に見落している点がある。そしておそらく、この問題を「ふつう」の人間に論じさせると、たとえフェミニストであってもこの点を見落すのではないかと思う。要するに私は「ふつう」ではないのだ。
それは、この教授連が妻帯者であるらしく、である以上彼らが犯したのは「強姦」だけではなく「姦通」でもあるという点だ。
配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と性行為を行うことを姦通という。むろんこういう強姦の場合、被害者に姦通の罪はない。
九年前、参議院選挙で自民党が大敗したとき、そのきっかけとなったのは、例の故・宇野宗佑首相の女性問題であった。宇野首相はかつてさる藝者と関係があり、その藝者に手切れ金を渡したのがけしからんとか言って藝者がマスコミに訴えたのである。どうしてこの藝者が宇野に恨みを抱いたのか、あるいはそれが「公憤」たりえると考えたのかよくわからないのだが、なんだかフェミニストが変な怒り方をしたり、別に悪いことはしていないという弁護論があったりした。しかしどうも私の知りえた限りでは、宇野首相が「不貞」を働いていたから悪い、と述べた人はいなかったような気がする。要するに宇野は妻がありながら別の女と「姦通」していたのである。とすると、妻があると知りながら姦通の相手をしていた藝者も同罪であって、訴え出られた義理ではないのである。そういう簡単なことが「ふつう」の連中にはわからないらしい。
では妻のある男を客に取る娼婦も姦通の罪を犯しているかと言えば、もちろんそうである(強制されているのでないかぎり)。戦前は「姦通罪」というのがあったが、これは夫のある女性が別の男と性行為することのみを罰するという男女不平等なものであった。だから男が娼婦や藝者と関係していてもそれが罪だという考え方が産まれなかったのである。
宇野首相退陣後ほどなく、海部内閣の官房長官山下徳夫が、やはり似たような事件で辞任したが、山下はその際「妻に済まない」と涙ながらに言っていた。罪を自覚しているだけ宇野事件の藝者なんかより天晴れであった。
だいたい、姦通罪を廃止したのが間違いだったのである。姦通罪は、男女平等に適用されるものとして復活させるべきである。トルコではじっさいそういう動きがあるそうだ。トルコに倣うべきである。そうなっていれば、板東八十助も近藤サトも畑恵も船田元も郷ひろみも今ごろ監獄のなかである。なんだかわくわくするではないか。こういうのを真に「文学的」というのである。「ふつうなら」とか「常識」を振り回す筒井や山口がちょっとも「文学的」でないゆえんである。だいたい、「不倫」がちっとも不倫らしくなく、ただいぎたないシロモノになってしまったのも姦通罪がないからである。配偶者以外とのセックスは逮捕覚悟でやってもらいたい。
秋田昌美『フェティッシュ・ファッション』
トップへ
男達の欲望は女性を男根化する事であるかもしれない。去勢コンプレックス的に言えば、男根のない女性は去勢されている。男性は女性の「男根の去勢された性器」を眺め、自らの去勢に対する恐怖と抑圧を作り出す。男性はこの恐怖を克服するために女性を幻想の中で男根化し、欠如した男根を彼女達に贈与する。女性の体の変形、衣服や拘束具によるフェティッシュ化は、失われた女性達の男根を彼女達の身体イメージの変貌を通して回復する作業なのかもしれない。女性達の「欠如」を通して男性が自己の権力を回復、維持しようという戦略こそが、男性社会の作り出すすべての性イメージに可視化されている。だが、女性を常に「欠如」として、性的な存在、「汚れ」の存在等々と位置づける事こそ男性の一人よがりの幻想であり、男性はいつも女性達の身体の権力と全一的な充溢性に圧倒され、彼女達の足下にひざまずく存在となる。ファリック・シンボルであり、「汚れ」をも意味する両価的な女性の「足」に踏み付けられる事は、女性を通してファロス的な全一性に対する畏怖感情を表し、なおかつ、「欠如」に位置づけられた女性の身体上に投影された他ならぬ男性自身の去勢という欠如を再補完する。こうして去勢された女性、これを男根化する諸々の手続き(女性をグラマラスな性に充満した身体存在とする事、権力的なミストレスに仕立て上げる事等々)、「性」が女性の身体上に目に見える形で外在化するための様々な言語的、イメージ的な操作を通して女性は男根的なセックスに包囲された存在となる。さらに、この男根的女性に圧倒される男性は、女性の分泌物や尻叩き等を通じて前ペニス的な幼児性愛の世界を保障する。女性に対して男性は常に幼児であるという幻想は去勢の対象となる男根がないユートピア的な世界を作り出す。だが、このエネルギーは社会の抑圧的男根体制を補償し、維持しつづけるために使用され、女性自体がアナル化される事はない。アナル化するのは常に男性の方である。
男根は男性の身体の中で外部へと突出した器官であり、男性はこれを自由に眺め、触れ、作動させる事ができる。男根はフェティッシュとして外部へ切り離すことができ、交換可能な存在である。女性の身体部位に対する様々なフェティッシュ化、交換可能な衣服、道具を通じての女性の身体の変形はすべて男根の外部性、流動価値性に意味づけられている。だから、男根は男性社会の欲望、作り出される身体イメージ、様々な衣服や道具によって構成されるフェティッシュ空間の中でゆき渡り、相互に交換でき、他の身体、フェティッシュと接続でき、アナグラムのように判じ絵になっている。
SM/フェティッシュの世界は、ある意味で男根的性幻想が最も過剰化された性の領域である。これらの世界ではあらゆる身体、あらゆる衣服、機具が男根的だ。ゆえに反ポルノ運動の女性達が最も攻撃する対象がSM/フェチである。だが、かつてのイメージが余りに明白に男根的であるがゆえに、女性こそがSM/フェチの世界を更新する。というのは、こうした世界は一方で身体の全感覚性や情感の形式性を必然的に要求する世界であるからだ。ここで延期されているのは男性器と女性器の結合を通して再確認される一方向的な性の階層秩序世界である。SM/フェティッシュの世界では男根は一つではなくすべての細部にばらばらになって散乱している。こうした男根の強度ゼロ平面的な世界では通常の性の階層秩序的な差異は生じない。SMに階層秩序的暴力の実現を見、あるいは、男性社会の誘惑する性器的存在に自己を託する事で、男女の性差的価値を強化しようとする女性の作り出すすごくノーマルな「SM」やノーマル・ポルノの世界とはまったく異なっている。ノーマル・セックスとその陰画でしかないノーマルなSM/フェチと、マニアが作り上げる本来のSM/フェチの世界をはっきりと区別する必要がある。マニアは自己の幻想を正確に何度も再現するための装置を必要とする。この装置は形式と倫理によって成り立ち、ルールによって支配されていなければならない。マニアである事、強要しない事が最大のルールであり、多形な相互の情念、欲望の形を承認し合う事で生れるコミュニケーションが重要だ。
SM/フェティシズムは見かけよりはずっと節度と倫理に支配された世界だ。
「本当にエキサイティングなSMやフェティシズムの世界では、友愛、気づかい、誠実さ、優しさ、尊敬、そして、時間が要求される」(”Skin Two” issue No.9,Tim Woodward Publishing Ltd.)
誰が鞭をふるうドミナントであり、誰が調教されるスレイブの役割を負っているかという事はさほど問題とはならない。それらはマイナーなルールであって、肝心な事は人が個々の規律、ルールに従いお互いがいかにしてモノに変貌する自由を獲得できるかという点である。SMは合意に基づく関係の中から出発し、ショーの主役となるドミナントもスレイブも彼/彼女の引き受けた規律を厳守し、役割を入念に演じる事に終始する。お互いはモノに化する機会を獲得する欲望を共有し、機会は公平に分配されるという期待の中に性的行為を生きている。おそらくB&D(ボンテージ&ディシプリン)がヘテロセクシャルな性愛の変形であるとすれば、その関係はバルトが述べる恋人達の一般的ないさかい/対話の関係にも似ている。「いかなるいさかいにも意味などありはしない。いさかいは、実践的でも弁証法的でもない。贅沢で無為なものなのだ。倒錯的なオルガスムスほどにも無分別なものである。跡を残すこともなければ汚すこともないのだ。パラドックスでもある」(ロランバルト『恋愛のディスクール』三好郁郎訳、みすず書房)
SMが二人のあるいは複数の他者と他者の間で演じられる性的なゲームであるとすれば、その関係はマゾヒズムに特有な契約関係に基づいているといえる。ドミナントもスレイブもまずマゾヒズム的であり、相互の関係に危機が生じるのは互いが気紛れなプレイの犠牲になる事ではなく、他者と他者との間の契約関係が破棄される事なのだ。
「誰もマゾヒストの役割を経た後でなければサディストではない。ほとんどのプロのドミナントは少なからずスレイブやマゾヒストであった経験を持っているものだ。人はマゾヒストでなかったならば、良いドミナントやサディストにはなれない。・・・もし、支配者が奴隷の欲望や要求の次元を超えてしまえば、彼等はもはやサディストではない。野蛮で悲惨な結果になる。SMは合意なのだ」(’Fakir Musafar Interview “Apocalypse Culture” Amok Press)
サディスト的理想が原則的に制度を破壊する事であれば、サディストは終局的にはゲームのルールに違反し、他者を破壊し、自己を破壊する事になる。サディストは掟破りなのだ。だが、性的行為におけるサディストは自らの役割を知っており、規律と節度の中で自己統制する。相手が消滅してしまえばゲームは終りだ。だから、この終りの感覚を永遠に延期する事、再びそこへ戻ってきて行為が再現できなかればならず、サディストは規律と秩序の中に身を置く事になろう。
「サドの暴力がやはり、痕跡を残すことがない。肉体はたちまち復元し、さらに新たな消耗にそなえている。痛めつけられ、毀損され、引き裂かれながら、ジェスティーヌは常に新鮮で、廉潔で、生き生きとしているのだ。いさかいのパトーナーも同様である。いさかいが終れば、何語ともなかったかのように生まれ変わるのだ」(ロラン・バルト、前掲書)
縄師と縛られる女の関係においてもそれを支配しているのはテクニックと節度、そして、信頼関係である。両者は互いの苦痛/快感を公平に分配しようと行為の中で努める。確かに苦痛/快感の質は公平ではあり得ない。だが、行為し労働する身体から生まれる友愛に似た結晶作用を両者が共有しようとする点においてはどちらも平等である。この場合も欲望は、この関係が再びどこかで生じうる期待性と再現の可能性の中で互いの身体の外側にあるもう一つの別の愛の秩序を目指している。規律、役割、衣服、道具、状況、身体の言語のコミュニケーションのルールが倒錯的な愛の形式には必要だ。様々な節度と倫理、そこへの服従はドミナントとスレイブが両者の可能的な権力行使の公平さを分配し合う事を巡って整然とした秩序を構成している。そこから無為の対話へ向けて出発するのだ。
~小林秀雄『常識について』より~
トップへ
今日のような書物の氾濫のなかにいて、何を読むべきかと思案してばかりいても、流行に書名を教えられるのが関の山なら、これはと思う書物に執着して、読み方の工夫をする方が賢明だろう。
小説の筋や情景の面白さに心奪われて、これを書いた作者という人間を決して思い浮かべぬ小説読者を無邪気と言うなら、なぜ進んで、たとえばカントを学んで、カントの思想に心を奪われ、カントという人間をけっして思い浮かべぬ学者を無邪気と呼んでいけないか。読書の技術が拙いために、書物から亡霊しか得ることができないでいる点で、けっして甲乙はないのである。サント・ブラウの教訓を思い出そう。「ついに著書たちは、彼ら自身の言葉で、彼ら自身の姿を、はっきりと描き出すに至るであろう」、それが、たとえどんな種類の著者であってもだ。ついに姿を向こうから現して来る著者を持つことだ。それまでは、書物は単なる書物にすぎない。小説類は小説類にすぎず、哲学書は哲学書にすぎぬ。
書物の数だけ思想があり、思想の数だけ人間が居るという、在るがままの世間の姿だけを信ずれば足りるのだ。なぜ人間は、実生活で、論証の確かさだけで人を説得する不可能を承知しながら、書物の世界にはいると、論証こそすべてだという無邪気な迷信家となるのだろう。また、実生活では、まるで違った個性の間に知己ができることを見ながら、彼の思想は全然誤っているなどと怒鳴りたてるようになるのだろう。あるいはまた、人間はほんの気まぐれから殺し合いもするものだと知っていながら、自分とやや類似した観念を宿した頭に出会って、友人を得たなどと思い込むにいたるか。
みんな書物から人間が現われるのを待ちきれないからである。人間が現われるまで待っていたら、その人間は諸君に言うであろう。君は君自身でい給え、と。一流の思想家のぎりぎりの思想というものは、それ以外の忠告を絶対にしてはいない。諸君になんの不足があると言うのか。
~丸山真男『日本の思想』より~
トップへ
K・レーヴィットはかつて、日本的「自愛」をヨーロッパの自己批判の精神と対照させて論じた(『ヨーロッパのニヒリズム』)が、彼のいおうとするところは、「愛国心」を失って思想的にも「自虐」に陥ったように見える戦後の状況にも必ずしも矛盾しない(その証拠に論壇でも最近いろいろな形でまた「自愛」復活のきざしが見える)。むろん私達はヨーロッパにおけるキリスト教のような意味の伝統を今から大急ぎで持とうとしても無理だし、したがって、その伝統との対決(ただ反対という意味ではない)を通じて形成されたヨーロッパ近代の跡を――たとえ土台をきりはなして近代思想に限定しても――追えるものでもないのも分かりきった事だ。問題はどこまでも超近代と前近代とが独特に結合している日本の「近代」の性格を私達自身が知ることにある。ヨーロッパとの対比はその限りではやはり意味があるだろう。対象化して認識することが傍観とか悪口とかほめるとかけなすとかいったもっぱら情緒的反応や感覚的嗜好の問題に解消してうけとられている間は、私達の位置から本当に出発することはできない。日本の「近代」のユニークな性格を構造的にとらえる努力――思想の領域でいうと、色々な「思想」が歴史的に構造化されないようなそういう「構造」の把握ということになるが――がもっと押しすすめられないかぎり、近代化した、いや前近代だといった二者択一的規定がかわるがわる「反動」をよびおこすだけになってしまう。
話がひろがりすぎたので、もとへもどすと、私達が思想というもののこれまでのありかた、批判様式、あるいはうけとりかたを検討して、もしそのなかに思想が蓄積され構造化されることを妨げて来た諸契機があるとするならば、そういう契機を片端から問題にしてゆくことを通じて、必ずしも究極の原因まで遡らなくとも、すこしでも現在の地点から進む途がひらけるのではなかろうか。なぜなら、思想と思想との間に本当の対話なり対決が行われないような「伝統」の変革なしには、およそ思想の伝統化はのぞむべくもないからである。
思想が対決と蓄積の上に歴史的に構造化されないという「伝統」を、もっとも端的に、むしろ劇画的にあわらしているのは、日本の論争史であろう。ある時代にははなばなしく行われた論争が、共有財産となって、次の時代に受け継げられてゆくということはきわめて稀である。自由論にしても、文学の芸術性と政治性にしても、知識人論にしても、歴史の本質論にしても、同じような問題の立て方がある時間的間隔をおいて、くりかえし論壇のテーマになっているのである。思想的論争にはむろん本来絶対的な結末はないけれども、日本の論争の多くはこれだけの問題は解明もしくは整理され、これから先の問題が残されているというけじめがいっこうにはっきりしないまま立ち消えになってゆく。そこでずっと後になって、何かのきっかけで実質的に同じテーマについて論争が始まると、前の論争の到達点から出発しないで、すべてはそのたびごとにイロハから始まる。また多少とも文花や世界観の本質に関係するようなテーマなどとは、問題の普遍性が高いにもかかわらずヨーロッパで長年とりあげられ究明されてきた思想的背景を――あれほど他方ではヨーロッパ産の作品が流出しながら――殆どまったく度外視して論争が行われることさえ少なくないから、「思惟の経済」の点でもはなはだ無駄なことが少なくない。ここには、(i)「完成品」の輸入取次に明け暮れする日本の「学界」に対する反動として他方で断片的な思いつきを過度に尊ぶ「オリジナルティー崇拝」がとくに評論やジャーナリズムの世界で不断に再生産され、両者が互いに軽蔑するという悪循環(これは後述するところと関連する)が作用しているし、また、(ii)各時代各集団が、その当時に西洋で有力な地位を占めた国あるいは思潮とそれぞれ横につながって、閉鎖的なヨーロッパ像を作り上げるので、縦の歴史的な思想関連が無視されるという事情もあり、(iii)現代ではいうまでもなくもっと単純な原因として、論争がマス・コミにとり上げられるときには、マス・コミの布いたレールに乗ったまま論争者の当初の意図からも遠ざかってしまうということがある。しかし、たとえば明治二十年代の有名なキリスト教徒と国體の関係をめぐる論争のように、仏教徒や儒教的思想家のキリスト教徒への論難の根拠が、幕末のいわんや十六世紀のキリシタン渡来の際のそれを発展させた跡がほとんど見受けられないということになると、やはり問題はヨリ一般的な日本思想史のパターンにまで拡大されざるをえないだろう。いうまでもなく「論争」はデアレクティークの原始的な形態であるから。
~富永健一『近代化の理論』より~
トップへ
十八世紀後半に産業革命を自力で生み出したイギリスは産業化において世界で最も早く、ナポレオン戦争後の一八二○年代に産業革命期に入ったフランスがこれに次ぎ、一八六一―六五年の南北戦争と一八七一年のドイツ統一後にそれぞれ産業革命期を迎えてアメリカとドイツは英仏よりもいっそう遅れるのですが、このような産業化における「先発」(earlistater)と「後発」(late starter)の事実がもつ意味については、経済史家が早くから着目していました。よく知られたアメリカの西洋経済史家ガーシェンクロンは、ヴェブレンの「借用された技術」(borrowed technology)という概念を援用して、後発国は技術を自分で開発する必要がなく、先発国のものを借りてくればよい点で有利であるが、しかし先発国の企業と競争し得るためには、一挙に大規模な企業を育成しなければならないので不利である、と論じました(Gerschenkron,1962:6-11)。
ガーシェンクロンの研究は西ヨーロッパの中で先発と後発の事例に関するものでしたが、最近ではイギリスの日本研究家として著名な社会学者ドーアが、イギリスの企業と日本の企業とを比較した研究の中で、ガーシェンクロンの上記の命題を追認するとともに、後発国であった日本は先進国に比してテクノロジーのギャップが大きかったので、それをはやく埋める必要から、イギリスのように現場の職人の経験に依拠せずに大学出の技術者に依存した、という違いを指摘しています(Dore,1973:293,339)。ガーシェンクロンもドーアも、後発国はこうした事情をもつゆえに先発国と同じ道をとることはできず、それとは異なった産業化の経路をとると主張したのです。
先発国と後発国を対比すれば、真に創造的なのは先発国である、といわなければならないことは明らかです。なぜなら先発国は、前例のないところですべて自力で生み出さなければならないからです。ガーシェンクロンはヨーロッパの場合について、ドイツやロシアの産業発展が真似事だとあざけられた事実を述べています。非西洋の日本がもっとそうであったことは、いうまでもありません。しかし、後発国が先発国をただ真似すれば産業化に成功し得るのだから先発国よりも有利であると言うことだけをいうのはけっして十分でないこともまた明らかでしょう。なぜなら、もしそうであるなら、先発国が産業化に成功したらすべての後発国はたちどころにそれを真似して、あっというまに先発国に追いついてしまうはずなのですが、現実の歴史的事実としては、後発国による先発国の追い上げはけっしてそのように早く簡単に進んだわけではなかったからです。このことは、西洋内部ではロシアや東ヨーロッパ諸国がいまだに西ヨーロッパ先進諸国に追いついていないことによって知られますし、非西洋では日本が西洋先進諸国に追いつくのに百年を要し、日本以外の東アジア諸国はいまだに追いつくにいたっていない、ということによって知られます。
じっさいガーシェンクロンもドーアも、まさにそのことを指摘したのです。すなわちガーシェンクロンが主張したことは、後発国の企業ははじめから先発国の企業と競争できるだけの規模をもたなければ産業化に成功し得ないということでしたし、ドーアが主張したことは、後発国はテクノロジー・ギャップを教育で埋めなければ産業化に成功し得ないということでした。これらの点は、非常に重要です。産業化における先発-後発の関係は、けっして後発国が先発国の歩いた道を同じパターンでただ遅れて歩む、という関係では有り得ないのです。つまり後発国の企業家は単に先発国の企業家の後追いをしているだけではだめで、独自の工夫をしなければけっして成功し得ないというのです。
以上のことに加えて私は、日本のような非西洋国の近代化と産業化は、ヨーロッパにおける後発国としてのドイツやロシアの場合とは異なる、もう一つの問題を背負ってきたことに注意を促したいと思います。それは、非西洋の近代化と産業化は西洋からの文化伝播に依存しているので、「西洋化」の問題、すなわち西洋とは違う社会の伝統をもちながら、西洋から社会と文化の伝播を受け入れるという問題に直面する、ということです。
~今道友信『西洋哲学史』より~
トップへ
マニアーという語は、今日でも生きていて日本語にもなっておりますでしょう。切手を集めたり切符を集めたりする人がいますが、はたからみますと、どうしてそういうことに大きな意味があるのか、分からず、常識はずれのように思われるのです。
そこで切手マニアとか切符マニアとか収集マニアというふうにいって、つまりは切手気違いと呼ぶわけです。それで、マニアという言葉は、俗語でも「ふつうではない」という意味で使われておりますが、医学では――狂というときに術語として使われています。ギリシア語ではマニアーというのは「狂気」ということなのです。
ところが、プラトーンは『パイドロス』という書物のなかで、そしてこの『パイドロス』という書物はプラトーンの思想でもあり、ソークラテースの思想でもあろうかと思うのですが、とにかくそのプラトーンの書物のなかで「人間のすることのなかで偉大なことというのは狂気によってのみ生じてくる」と、このようなことをいうのです。狂気には二つある。一つは病気による気違い、この病気による狂気というのは、プラトーンは価値としては否定するのです。しかし、それとは別に、神がかりの狂気というのがあるとプラトーンはいうのです。
それはどういうことかというと、神がおのれのなかに人をとらえてしまう。「神のなかに人がとらえられてあること」すなわち、「入神の境」ということを、ギリシア語でエントゥーシアモス(enthousiamos)というのです。これは英語の「恍惚」とか「有頂天」とか訳しているenthusiasmの語源でございます。enというのは「なかに」という意味です。thouというのは、テオスが神で、その変形です(神学などでテオロジーともうしますでしょう)。ですから神theouと関係します。ισμοζというのは、なになにイズムというときに使われる語尾で、その前に置かれた語意を強調するものです。ですから、これは「神のなかにあること」「入神の境」という意味です。まさにそれが大事だとプラトーンは申します。そして、「神のなかにある」というのはどういうことかというと、神がかりになって、その神の力量にとらわれた状態になり、そこで、神しかみないイデアそのものをみることができる状態のことだ、と『パイドロス』のなかでプラトーンは説くのです。
たとえばエロース(eros)の神にとらわれると人はどうなるか。エロースというのは、今日、エロチックといわれているものの語源ですから、性愛や肉欲という意味です。エロースの神にとらわれるとどうなるだろうか、それはふつうの人からみると気違いにみえるというのです。それはそうでしょう。
学生がよく生き生きとして「選んだ人をみてください」といって連れてくることがあるのです。たしかに、多くの場合、それでいいのですが、私どものようにだんだん年齢が高くなりますと、若い男女への点数もきびしくなります。何もその程度の人のために一生をささげなくともと、つい思うようなこともあります。「君、もっといいのが見つかるかもしれないから、まだ若いのだし、今のうちは勉強したらどうだ」と言いたい口を押さえて、「おめでとう」ということもときにはあります。
しかし、そういう私の考えは凡人のあさはかさであって、本当にエロースをもっている人は、その人に対して愛をもっているときには、愛をもたない人が発見することのできないよさをみているのだと思わなければならないのでしょう。その人しかわからない相手のよさ、そのよさを発見するということ、これはエロースの力のせいです。異性に対する知識というのはどこから出てくるかというと、概念的な認識でもなければ、客観的な記述でもなくて、エロースによって高められた心でみたときに、ふだんはみえない相手のよさがわかってくることがある。そして、そのよさのために、たとえ自分は一生を棒にしてもかまわないと思う。それはエロースの認識のすばらしさだといわなければなりません。
だから、エロースにとらわれて、この世のことはすべて捨てても、その人のために尽くすということは、はたの人からみたら、マニア、気違いにみえるかもしれない。有島武郎の『或る女』における葉子と倉地の関係など、まさしくそういうものでしょう。それゆえ、それは説明できないけれども、エロースの神に高められて、その神の力によって相手のよさをみているのだということができなくもないでしょう。
~竹下敬次・広瀬京一郎『マルセルの哲学』より~
トップへ
技術的理性は考察するものを、自分の前にひきすえる。そしてそれを客観的に捉えようとする。客観的ということは、いいかえれば、主観をまじえずに、ということであろう。もちろん知るというはたらきである以上、主観をぬきにすることはできない。けれども、知る内容に関しては、そこに主観の影響、少なくとも個々の主観によって違ってくる偶然的な要素の影響は、排除しなければならない。
しかし、このようなことはいうまでもなく、知る者と知られるもの、主観と客観とが、おたがいに独立しているときに、はじめて要求できることである。けれども、問題によっては、そのような分離が本来不可能であり、人為的にそれを強行するときには、その問題自身が変質してしまうような場合もある。
たとえば、この私は何者であるか、というような問題。私たちのおそらく大部分が、青春のめざめのころに一度は遭遇したはずの、この問題をとりあげてみよう。私たちは日々の生活にかまけて、そんなことはいつか忘れてしまっている。哲学は、このような解決されないままに、意識の下積みになって忘れ去られた問題を、白日のもとへ引きずり出して、私たちに対決をせまる。
ところで、この問いは、<あなたは何者ですか≠ニか、<彼は何者ですか>という問いのように、客観的な解答を与えることができない。なぜならここでは、このように問いかけている私自身が、問われているからである。いいかえると、問う者と問われるものとが同一であるために、これを主観と客観とに分離対立させることができないのである。
もしこの分離を強行して、問うている私と問われている私とを対立させ、私という一人の人間を客観的に捉えようとするならば、それはあなたや彼についての同様の問いと同じように、さまざまの客観的な答えを得ることができるだろう。私は日本人である、私は学生である、私は美人である、等々。
だがこのような言い方が、あの最初の問題の答えにならないことは明瞭である。それは、子供に見なれない花の名前を聞かれて、<それは花さ>といいまぎらわすことのように、答えるのではなく、問いをはぐらかしているにすぎない。
じっさい、そこで問われていたことは、私という一人の人間の人種や職業や美醜などではなく、むしろこのように自分自身を問題にする、あるいは、せざるを得ないこの私は何者なのか、ということではなかろうか。いいかえれば、自分自身の存在についてその意味を問うことを、私の本性が許す、あるいは強いるというようなことが起こるのは、この私がどういう存在であるからなのか。これがこの<私はいったい何者であるか>という問いの意味でなのではないか。
そうしてみると、ここで、問われている問題自身が、問う者自身を自分の中へ引きずり込む、あるいは、問う者自身が問われている、という事情が明らかになるだろう。
~都筑卓司『物理学はむずかしくない』より~
トップへ
ご存知のように物質を最後の最後まで分割していきますと、分子に、さらに原子に到達します。物質はもちろん人間や生物をふくめて、非常に多くの原子の寄り合い世帯である・・・ということは、すでに常識になっています。ところで、いきなり問題を提起するようですが<原子、原子、というけれど、本当にその原子とかいうものは実在するのでしょうか>と聞きなおられたらどうでしょう。<ほんとうも嘘も、いまさらそんな幼稚な質問をしてどうなるものでもなかろう。どの書物を見たって、ちゃんと書いてあるではないか>と反論されるのが落ちです。
しかし、ちょっと待って下さい。私は学生時代に―旧制度の高等学校のころでしたが―自然科学系の教授が、次のような話をされたことを今でも覚えています。<ものは分子や原子からできているといわれているが、この分子や原子に対する考え方には三つの方法がある。そうしてこの三つのうちのどの考え方をしているかによって、その人間が利口か、そうでないかが決まってくる。もっとも利口ではないものは・・・つまり一番馬鹿な人間は、分子や原子がほんとうに≪ある≫と思っている。利口と馬鹿の中間は・・・いうなれば中ぐらいの頭の人間は、分子や原子は≪概念≫だと考えている。それでは利口な者はどう思っているのか。利口な人間は、分子や原子とはたんなる≪約束≫だと信じているのである・・・>。
三十年近くも前の話ですが、私はこの言葉をきわめて印象深く記憶しています。原子爆弾の話の時にも述べましたように、私たちは原子についてある程度の知識はありました。習いはじめのころは、多少とも奇妙なもの、あるいは神秘的な話・・・というような気がしましたが、理科系の学生だった私は、やがてはそれが当然の事実・・・というような受け止め方をしていたのだと思います。そこへ、思いもかけずに、<実在>、<概念>、<約束>という三通りの言葉で説明されて、何か今までに経験しなかった、あるいは今までに教わらなかった斬新なものの見方を示されて、驚くと同時に、それまでの自分の考え方が枠にはまった固定的なものであることを反省させられたわけです。
(中略)けっきょくこの話を要約してみますと、分子とか原子とかがほんとうに存在すると考えて疑うことを知らないという思考形態はきわめて皮相的なものであり、実際にはそのようなものではなくて<約束事>にすぎないのだ・・・ということでしょう。それに対して両者の中間派として、<実在>というほど具体的ではないが、といって<約束>といいきるほど根拠のないものではない・・・と思っている人たちは、分子、原子は自然科学を学ぶ上での一つの考え方、つまり<概念>だとしている、というように話されたわけです。
~高垣忠一郎『思春期の心理』より~
トップへ
思春期におけるめざましい心身の成長、発達と、それにともなう社会的、環境的条件の変化は、思春期の心の中にさまざまな新しい欲求を生み出し、時にそれらは矛盾し、葛藤し合います。その結果、もう一度自分自身を捉え直し、自己を方向づける必要が生じてきます。思春期の自己自身を見詰め、自己の在り方を探ろうとする欲求は、そういう必要性から生じてきます。
思春期以前の子供、自分自身を対象化して見ることはできます。しかし自分自身を見詰めることは困難です。思春期の<自我のまざめ>は、自分自身を見る<もう一人の自分>を自覚することによって、それが自分自身を見詰める<もう一人の自分>へと深化し、発展することを可能にします。
すでにふれましたように、思春期には自分自身を対象化して考えることができるばかりでなく、さらにその考えている自分を自覚し、反省することができるようになります。たとえば、自分自身について考え、それを日記に書いたりするばかりでなく、その自分自身について書いたことがなんとなくウソに感じられるという思いが生じることがあるのは、その一つのあらわれだと言えます。
それは、自分自身を対象化して見る自分の視点を、さらに批判的に反省することから生じることがらです。すなわち、自分自身を<かくかくしかじかである>ととらえている、その捉え方をさらに反省的に捉え直すことができるということです。
このように、自分自身を見ている自分に気付き、それを自覚できるということは、すなわち、自分自身を見ている視点を反省的に捉え直し、相対化することができるということです。それは、こういう見方をすればこういうふうに捉えられるのが、別の見方をすればまた違ったふうに捉えられる、というように多面的なものの見方ができ、いろいろな角度から自分自身を見詰めることができるようになることを意味します。
~永井均『これがニーチェだ』より~
トップへ
なぜ人を殺していけないか。これまでその問いに対して出された答えはすべて嘘である。道徳哲学者や倫理学者は、こぞってまことしやかな嘘を語ってきた。ほんとうの答えは、はっきりしている。<重罰になる可能性をも考慮に入れて、どうしても殺したければ、やむをえない>――だれも公共の場で口にしないとはいえ、これがほんとうの答えである。だが、ある意味では、これは、誰もが知っている自明な真理にすぎないのではあるまいか。ニーチェはこの自明の真理をあえて語ったのだろうか。そうではない。彼は、それ以上のことを語ったのである。
世の中が面白くなく、どうしても生きる悦びが得られなかった人が、あるとき人を殺すことによって、ただ一度だけ生の悦びを感じたとする。それはよいことだろうか。それはよいことだ、と考える人はまずいない。あたりまえだ。殺される方の身になってみろ、と誰もが考える。そんなことで殺されてしまってはかなわないではないか。
だが、ほんとうに、最終的・究極的に、殺される方の身になってみるべきなのだろうか。自分その悦びの方に価値を認めるという可能性はありえないのか。このように問う人は、まずいない。だが、ニーチェはそれを問い、そして究極的には、肯定的な答えを出したのだと思う。だからニーチェは<重罰になる可能性をも考慮に入れて、どうして殺したければ、やむをえない>と言ったのである。彼は、<やむをえない>と言ったのではなく、究極的に<そうするべきだ>と言ったのである。そこに相互性の原理を介入させる必要はないし、究極的には、介入させてはならないのだ。そうニーチェは考えたのだと思う。
つまり、反社会的な善というものがあるのだ。いや、あるどころではない。善とは、最終的・究極的には、反社会的なものなのである。いや、あるどころではない。善とは、最終的・究極的には、反社会的なものなのである。だから、世の中のためになることをもって善とし、世の中に害を与えることをもって悪とする、これまでの倫理学説は、すでにひとつの倒錯なのではないか。煎じつめれば、これがニーチェの問いである。
~永井均『<こども>のための哲学』より~
トップへ
ぼくは大学では、いろいろな理由から、哲学ではなく倫理学を専攻したのだが、まったく驚いたことに、倫理学という学問は、予期に反して、ぼくの疑問に少しも答えてくれなかった。はじめのうちぼくは、たまたま教わった先生がよくないのかと思ったが、そうではなかった。当時出版されていたどの教科書を読んでも、何の助けにならなかったし、それどころか古典的名著とされているものを読んでみても、ばかばかしいほどつまらないことしか書いてなかったからだ。ぼくにはここでもまた、ぼくの問いがふつうに問われていない問いであることを痛感させられたのである。
(中略)それにしても、ぼくが学んだ倫理学という学問は不思議な学問だった。哲学の場合、ぼくはそこに自分の問いに対する答えを見つけることはできなかったとはいえ、他の人たちがやっている哲学というものの意味がよくわかったし、彼らの態度や意気込みには、むしろ共感を感じた。だが、倫理学に関しては、まったく事情が違っていた。ぼくがそこに見たのは、道徳現象に関してどんな上げ底も感じたことのない人たちが集まって、常識というそれなりにすなおな素顔のうえに、無用な厚化粧をほどこしている、といったような気味の悪い風景だった。ある宗教の家系に生まれながら、その宗教の教義に疑問を持ってしまった者が、その疑問をはらすために、教義学者に弟子入りしてしまったみたいなものだった。
教義学者はその宗教の根本前提を(ふつうの信者以上に)疑わない。仏陀がさとりを開いたとか、イエスが神の子だとかいった根本前提だ。ぼくにはそういった根本的なところが問題だったのに。要するに、教義学者は素朴な信仰のうえに厚化粧をほどこすだけなのだ。
イデオロギーとは、ことがらの実態を明らかにするようなふりをして、実はある何かを正当化するためにできている説明体系のことだ。このイデオロギーは「なぜ悪いことをしちゃいけないのか」といった問題そのものを認めない。それは、根本前提だからだ。だから、この学問を学んでも、何かが明らかになることはない。倫理学は、現に存在している道徳がどんな構造をしているか、を解明することが、同時に、人は何をなすべきであるか、いかに生きるべきであるか、を教えることができる、という前提の上に成り立っている。つまりそこでは、道徳の本質の究明と、従うべき道徳規範の提唱と、人生論とが一体となっているのだ。
たとえば言語の場合、文法書や辞書は、正しい言葉使いをしたければこう使え、ということを教えるだけである。倫理学だって、道徳的に正しい行為をしたければこうしろ、ということがいえるだけで、道徳的に正しく行為しろ、などとはいえないはずなのに。あるひとつのものの考え方が、ある問いの存在そのものを認めようとしないとき、そのことのうちに、そのものの考え方の本質を読み取らなければならない。あるイデオロギーが、ある問いの存在を認めないとき、そのことのうちに、そのイデオロギーの存在理由を読み取らなければならない。また逆に、その問題の存在そのものを認めようとしないようなものの考え方が世の中を支配しているとき、その事実のうちに、その問題の本質を読み取らなければならない。
つまり、倫理学は道徳というものの本質を究明する学問なのではなく、それ自体が道徳的な学問なのである。道徳についての真実を語ろうとする学問なのではなく、道徳について道徳的に語ろうとする学問なのだ。教義学がある信仰についての真実を述べる学問ではなく、ある信仰についての信仰を述べる学問であるのと同じように。もちろん、教義学者はそれを真実と信じているのだが。ぼくはそのことをあやしんだ。道徳についての道徳的発言、善についての善なる言説なんて、ほんとうに必要だろうか。それは単なる厚化粧じゃないか。そんなもの、ないほうがよほどすっきりする。
でも、あるときぼくは気づいた。そうではないのだ。それは絶対に必要なものなのだ。道徳という制度には、それを褒め称えてくれる翼賛的イデオロギーがなくてはならないのだ。そういうのがなくては、人間は自然な同情心を超える範囲まで、自分によって好いことと世の中にとって好いことを重ね合わせる動機が持てないからだ。つまり、倫理学が言っていることは全部<うそ>だけど、でも、それはぜひとも必要な<うそ>なのだ。
立川ヨガ 立川エリア唯一の溶岩ホットヨガスタジオ「オンザショア」

| 【監修者】 | 宮川涼 |
| プロフィール | 早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻修士号修了、同大学大学院同専攻博士課程中退。日本倫理学会員 早稲田大学大学院文学研究科にてカント哲学を専攻する傍ら、精神分析学、スポーツ科学、文学、心理学など幅広く研究に携わっている。 |